サイト管理人のブログです。
ブログ
ブログ一覧
鍼灸国家試験 出る順経穴
受験生の皆さん追い込みですね!
私は、鍼灸国試対策予備校で講師してます!
主に東洋医学、東洋医学概論、はりきゅう臨床論、経絡経穴概論、はりきゅう理論を担当して授業を行っております。
また、個別指導は国家試験対策や、進級対策として全部の教科を受け持っております。
いつでもご相談受け付けておりますのでご連絡ください。
さて、鍼灸国家試験も残すところ10日を切りました。
私が調べた、過去の国試問題より、出る順経穴ベスト10を発表したいと思います。
まぁ10個だけなので、これからの時間でも覚えられるでしょう。
あくまでも、私が調べたので
ご利用はご自身にお任せします
合谷(ごうこく)
取穴部位:第1・第2中手骨底間の陥凹部、第2中手骨より要穴:原穴、四総穴筋肉:第一背側骨間筋運動神経:尺骨神経知覚神経:橈骨神経浅枝血管:第一背側中手動脈
多いですね 一位ではないですが数多く出題されています
取穴部位や要穴はしっかり覚えましょう 四総穴は大事です
曲池(きょくち)
取穴部位:肘を屈曲してできる肘窩横紋の外方で、上腕骨外側上顆の前要穴:合土穴筋肉:長橈側手根伸筋、短橈側手根伸筋運動神経:橈骨神経知覚神経:外側前腕皮神経血管:橈側反回動脈
骨度法の出題ではランドマークとして度々しゅつだいされています
中脘(ちゅうかん)
取穴部位:神闕穴の上4寸、梁門穴、陰都穴と同じ高さ要穴:胃経の募穴、腑会筋肉:白線知覚神経:肋間神経前皮枝血管:肋間動脈、上腹壁動脈
胃の募穴、腑会など、また腹部のランドマークとして骨度法の出題、腹部横並び経穴など出題が多数です
太白(たいはく)
取穴部位:足の第1中足指節関節の近位陥凹部、赤白肉際 要穴:兪土穴、原穴筋肉:母趾外転筋運動神経:内側足底神経知覚神経:浅腓骨神経血管:第一背側中足動脈の枝
取穴関連の問題で出題が多いです。脾の兪土原穴としての問題もあります。
足の第1中足指節関節の近位陥凹部 (近位ですからね)
太淵(たいえん)
取穴部位:手関節前面横紋の橈側端の陥凹部、橈骨動脈拍動部要穴:兪土穴、原穴、脈会筋肉:屈筋支帯知覚神経:外側前腕皮神経血管:橈骨動脈
肺経の中の最重要穴 太淵!ランドマークとしての出題多いです。
足三里(あしのさんり)
取穴部位:膝を立て、犢鼻の下3寸、脛骨粗面と腓骨頭下際の間要穴:合土穴、四総穴、足の陽明胃経の下合穴筋肉:前脛骨筋運動神経:深腓骨神経知覚神経:外側腓腹皮神経血管:前脛骨動脈
鍼灸学校で初めて他人に刺すのが、足三里かと思います。出題は多いです。
天枢(てんすう)
取穴部位:臍の外2寸要穴:大腸経の募穴筋肉:腹直筋運動神経:肋間神経知覚神経:肋間神経前皮枝血管:浅腹壁動脈、下腹壁動脈
神闕(へそ)並びとしての出題が多いです。前正中線外方2寸
大腸の募穴 しっかり覚えておいてください
委中(いちゅう)
取穴部位:膝窩横紋の中央要穴:合土穴、四総穴、足の太陽膀胱経の下合穴筋肉:膝窩筋、足底筋運動神経:脛骨神経知覚神経:後大腿皮神経(総腓骨神経幹が走る)血管:膝窩動脈
ランドマークとしても出題されますし、四総穴としても
膝窩動脈を忘れないでください
陽陵泉(ようりょうせん)
取穴部位:膝をたてて腓骨頭の前下際要穴:合土穴、筋会、足の太陽膀胱経の下合穴筋肉:長腓骨筋運動神経:浅腓骨神経知覚神経:外側腓腹皮神経血管:外側下膝動脈、後脛骨動脈の腓骨回旋枝
胆経で唯一ランクインしました、近年ではテスト法と組み合わせての出題があります。
神門(しんもん)
取穴部位:手関節掌側横紋の尺側にあり、豆状骨の上際で尺側手根屈筋腱の橈側要穴:兪土穴、原穴筋肉:尺側手根屈筋腱運動神経:尺骨神経知覚神経:内側上腕皮神経血管:尺骨動脈
心経は、0.5寸きざみなのも要チェックです
これらは過去の国家試験で30問ほど出題されています。
一番多い経穴は50回近くです
あと少しですが、全力をつくしてかんばってください
在学生や、既卒者の方は勉強みますのでご連絡ください
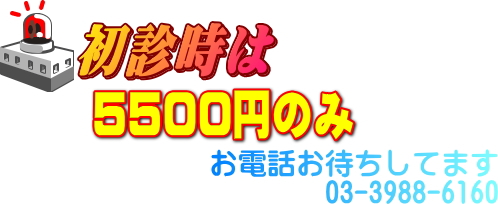
鍼灸学生や受験生の方は治療時に申し出てください
出る順経穴のパスワードや受験のアドバイスもします
遊びにきてください
統合医療展
1/24に、東京ビックサイトで行われた統合医療展に、日本鍼灸師会として参加してきました。
鍼灸治療の体験コーナーを担当し、多くの方々に体験していただきました。

ほとんど方が肩こりに悩んでおり、手際よく鍼を打つと、すぐに変化を感じてくれました。

大便溏薄(だいべんとうはく)
大便溏薄とは、水様便よりはやや固形物が多い状態の便
溏( 凝固しない,半流動の )薄(薄い)
水様便
水じょうの便
大便難 便秘の事
大便秘結 便秘の事
大便不通 便秘の事
大便閉 便秘の事
大便燥結 大便が乾燥して排泄が困難なもの
大便初鞕後溏 だいべんしょうこうこうとう
初め硬くてあとはゲリな状態の大便
鍼灸治療では便秘の治療と下痢の治療が同じ事をしたりします。
なんだか変な感じですね
東洋医学は原因を治す事を目的としているので
便秘も下痢も原因が同じだった場合は同じ治療方法を選びます。
脾 胃 大腸 小腸 寒熱 湿 陰虚 気虚 陽虚 この辺りはしっかりと抑えて国家試験に臨んでください
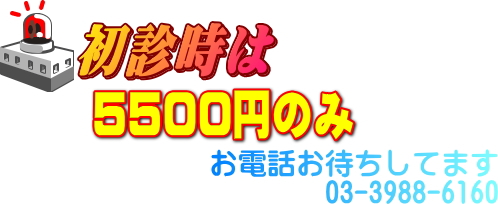
鍼灸学生や受験生の方は治療時に申し出てください
出る順経穴のパスワードや受験のアドバイスもします
遊びにきてください
百脈を朝ず(ひゃくみゃくをちょうず)
肺朝百脈
肺の働きの一つ
肺は百脈に通じ、治節を司る。
朝には「集まる」の意味
百には「多い、全て」の意味なのでこの場合は「全身の脈」となる。
肺朝百脈とは、肺が全ての血液を集め、肺の呼吸により気体交換を行った後に、再び全身に向かって布散すること。
百脈を朝ず(ひゃくみゃくをちょうず)は肺と覚えましょう!⇐国試
呼吸に関係する臓は肺と腎と言うのも忘れがち!
腎は「納気」
吸気を補助して、深く息を吸い込ませ、呼吸のバランスを保つ機能の事。
納気の失調で
深い呼吸ができない・咳嗽・喘息・呼吸困難 ⇐国試用
頑張れ受験生
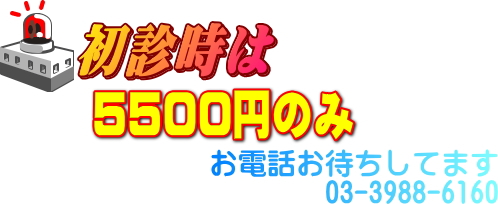
鍼灸学生や受験生の方は治療時に申し出てください
出る順経穴のパスワードや受験のアドバイスもします
遊びにきてください
鍼灸治療がなぜ効くのか~鍼灸理論~
一月も半ばになり、治療院には、新しい方々が治療に訪れていただいております。
治療に訪れた方に、なぜ鍼灸治療が効くのかという事をお話しております。
また、二月末には鍼灸国家試験があり、先日は鍼灸理論の特別授業を担当した事もあり、この辺りを記しておこうと思いました。
一般の方向け ~鍼灸がなぜ効くのか~肩こり
人間の身体には筋肉があり、運動は全て筋肉の収縮が関わっています。筋肉への命令には脳からの指令が神経線維を伝わり、筋肉に達すると力が入ります。もう一つは自律神経の関与です。筋肉内の血管などは全て自律神経が支配しており、血液の流れなどを管理しています。自律神経には交感神経と副交感神経があり、交感神経は主に闘うまたは動く時に優勢に働きます。副交感神経は食事や、睡眠などのリラックスするときに優勢に働きます。交感神経は筋肉を緊張させます。これが続くと末梢血管が収縮し、筋緊張が亢進し、その結果肩こりが発生すると考えられています。
鍼灸治療が肩こりにどうして効くか?
筋肉の固さには様々な因子が関与しています。神経の活動状況や、筋肉が含む水分量などです。
この筋肉の硬さを指標として、鍼灸の実験は様々な方法で行われてきました。
我々鍼灸師は、この筋肉のコリを硬結と呼び、そこに鍼を刺入し、1Hzで刺激すると、このコリが緩む(筋肉の硬さが柔らかくなる)という事を鍼灸学校で習います。筋肉を緩ませる一つの手法です。
筋交感神経の活動を抑制する事が報告されています。鍼刺激により、CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)が、神経終末から放出され筋肉血管を拡張する事も確認されています。
また、 下降性疼痛抑制系 という鎮痛効果も鍼灸治療では得ることができます。これらは人に備わった機能であり、鍼灸治療はそのスイッチをいれるお手伝いをしていると考えます。
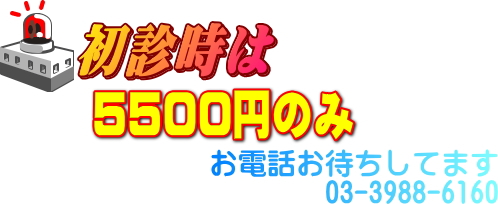
と、こういった科学的に研究されている事が国家試験に出題されています。
ですが、東洋医学的、鍼灸治療効果の説明もあります。
お客様の好みにより、上記のような生理学的な説明と、東洋医学的説明とご用意してお待ちしております。
寒くなってきました。自律神経調整で来院する方が増えてきました。
お気軽にお問合せください。

